アクアリウムに吸いついた大きな手。その手の内を流れゆく血の色が妙に赤いとナミは思う。冬を彩る無人島に船をつける少し前から、ルフィの手は赤みだした。自身の手の甲の白さと見比べてみれば余程ルフィのそれは熱を持っているように見える。その染まった手のひらを水槽にべったりと貼りつけて、ルフィはさっみいなあと呟いている。ナミは紅茶を一口啜って、頭上から時折聞こえてくる騒がしい声に耳を傾けた。ウソップとチョッパーが小一時間程前から釣りを始めたが、この寒い海ではいまだ一匹も魚が落ちてくる気配はない。ナミが飲み始めた紅茶も後一口二口飲めばカップの底が見えそうだった。底に沈殿した葉を揺らしつつナミは立ち上がった。そのとき、ルフィから空気の抜けたような声が漏れた。魚、きた。ぼうとした曖昧なその声に、ナミも水槽の中を見つめてみる。よく目を凝らさないとわからないほどの小さな赤い魚が一匹増えていた。金魚によく似たそれは居場所を求めるかのように縦横無尽に泳いでいる。ルフィはその動きを目で追いながら、白い息を吐き出した。寒いからかな。そう言った。ナミがルフィの横顔を見下ろすと、ルフィの頬には水槽の揺らぎがはっきりと映っていた。魚たちの影がルフィの瞳の中を蠢いている。そのなかでも赤く小さな金魚みたいな魚は居場所を決めたのか、ルフィの瞳の中を泳いだ。ルフィはその魚を見つめ言う。こいつが落ちてきた途端、水の色が変わった。ナミには、水槽のなかの元々の色も覚えてはいなかったので、何がどう変化したのかわからなかった。ただアクアリウムの輝きがナミの眼球を収縮させたのみ。寒いからだろうな。ルフィがもう一度呟く。彼の手は赤みを帯びたまま。
夜。クルーたちが自由に過ごす時間帯。ナミが測量机で航海記録をつけていると、ふと部屋に光が差した。棚に並べられた本の背表紙に、細長い光がゆらゆらと靡いている。そこですべらしていた羽根ペンを置きナミが振り返ると、扉がほんの少し隙間を覗かせている。扉に近付き隙間から外を窺うと、もう大分日が暮れていた。入り込んだ風の冷たさに身震いし、椅子に掛けてあった上着と手袋を着け測量室から出る。ナミが外に一歩出た途端、ふわりと頬に水が当たった。見上げると、サニー号の頭上には巨大な雪雲。無意識に背中を丸めてナミは辺りに目を配る。ひととおりクルーたちが何をしているかを確かめて、ナミは白い息を散りばめた。あいつだけ、いない。それに気付いて、すぐ展望室に足を向ける。梯子をゆっくりとのぼって中に入ると、ゾロがベンチに腰掛けて凍りついたタオルを前に辟易しているところだった。ナミが入ってきたことに気付き凍ったタオルを床に置いたゾロは、この雪は一晩中降るのかと聞いた。おそらく降る。答えてからナミは尋ねる。ねえあいつは?砂浜。短く返されたその答えに窓に近付いて外を見る。砂浜の端をゆらゆら歩く背中が小さくナミの目に飛び込んでくる。何やってんのあいつは!思わず声に出すと、ゾロがルフィの代わりとばかりに答えを寄越してきた。此処の海は独特の色だから見に行くっつってたな。
海水が足首を攫った瞬間、あまりの冷たさに飛びのいて、すぐさま砂浜に逃げた。その砂浜も雪に埋もれつつあるのでナミは手に持っていたブーツを履く。よくこんな中をあいつは……とぶつぶつ文句を垂れながらナミが前方を見ると、数メートル先をルフィが歩いている。ルフィの足跡が雪が混じる砂浜にきっちりと残されていて、ナミもその足跡を辿るように後を追う。すっかり暗くなってしまった。サニー号から漏れ出る光がなければ足元もおぼつかない。ちらつく雪が、吐き出す息も凍らせてしまいそうで自然とナミの歩幅も広くなる。フードをかぶり、次第に息もあがる。それなのに前方で立ち止まったルフィの背中は微塵も揺れない。雪がもたらす静寂のせいか、ルフィから漏れる息遣いまでナミには聴こえてきそうだった。その視線が海に空に波打ち際に向けられている。ナミも自然と同じ方向を見て、考えた。ルフィが見つめる海には、季節が存在するのだ。色が存在する。鼓動も聴こえる。そう考えると其れが見えるような錯覚。海の季節、此処では冬。孤独をごまかすように大きく吐き出される波の鼓動、そして押し寄せる闇色の気配。こうして海の一点を眺めていると急におそろしくなり前進することができない。まるで自分が海の一部にされるのではないかと飲まれるのではないかと堪らない気持ちになる。しかしルフィは其処に立つ。呪われた身体をもちながら、彼を自分のものにしてしまうため襲い掛かる波打ち際で、揺れることなく立ち続け、ぎらぎらとした目を此処ではない何処かに向ける。あいつはいつも闘っている、闘っているから見えないものも見えるのだ。ふと気配がして足元を見るとアクアリウムのなかを息苦しそうに泳いでいた赤い魚が、ぴたぴたと浜辺で息を求めていた。其れを見てルフィを追うことをやめ、自身の手袋を脱ぐと其の赤い魚の隣に其れを置いた。そうして船に戻る方向に引き返す。辿ってきた二人分の足跡は、もう波に攫われて跡形もなく滅んでいた。まるでそれを見計らっていたかのように、サニー号の展望台から光が消えたのが見えて、ナミは凍った唇を緩めた。切れた其処から血の味がする。
翌日の朝。ナミがシステムキッチンで珈琲を飲みながら新聞を読んでいると、ルフィが激しい音を立てながら入ってきて、サンジにどやされつつ、ナミの隣に座った。ちらと横目で見ると、ルフィの手にはナミの手袋が嵌められている。小さめの其の手袋は、ルフィの親指の付け根あたりまでしかない。雪やんだな!ルフィは白い歯を見せて、機嫌がいい。新聞の同じ箇所を何度も何度も読み返しながら、ナミは珈琲を啜った。その苦い味は昨夜の血の味と似ている。
その日の午後サニー号は出航し春を迎えた。冬を溶かす気温の中、ルフィは其の手袋を決して外そうとはせず赤い魚は水に溶けてしまった。
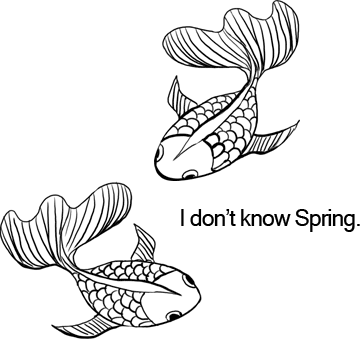
100123:motchさん(@the Pinkpants)へ、愛を込めて。
101006:motchさん(@the Pinkpants)デザインタイトルロゴ!